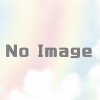狙いは良い中高か最終学歴か
はじめに
受験の低年齢化が叫ばれて久しいですけど、いい中学校に入れないとエリートコースは無理、という風潮が感じられるのですが、全く以って違います。偏差値50の学校しか受からなかったからウチの子才能ないわ、とおっしゃる親御様などがいて・・・。
どのステージを狙うのか
受験といえば一般的に中学受験、高校受験、大学受験の3つがありますが、それぞれの受験は少し回り道があります。中学受験で必要とされる知識の中には「どうせ中学で勉強するじゃん」という内容も多く含まれており、高校受験で勉強する内容には「大学受験には出ないッス」も結構あります。ただし、「より高い所を目指す空気」はより高い学校しか持っていないことが多いので、「やる気」とか「エリート意識」とか「有能感」とかの育成には楽チンなことも多いですよ。さて、さあ今からエリートになりたい、と言い出したとき、どこを狙うのか、はかなり重要です。小6の5月に中学受験を目指した場合、かなり厳しい戦いになりますよ。同じく、中3の6月から塾に入ってハイレベル高校を目指すとなると、偏差値60程度なら何とかなるかもですが、それ以上となるとなかなかハードです。
地元の公立小学校からハイレベル中学を目指す前に
小5や小6から目覚めた場合は中学を狙うことと高校を狙うことも視野に入れておいたほうがいいかもです。中2~3から目覚めた生徒は良い高校に入ることとと同時にいい大学に入ることも視野に入れておいたほうがいいかもです。できるだけ視線を先に持っていたほうが逆算がしやすいので、何事にも有利に運べる印象です。でも子どもが一人でこの長期計画を立てたり実行したり進捗状況を把握したりというのは難しいので、そこは親御様かプロの出番となります。小6の5月ですと入試まで7~8ヶ月です。その時間で小4~6の4教科の基礎勉強をこなしテスト前対策をしなければなりません。しかし高校入試を念頭にするなら3年8ヶ月の猶予があります。中学受験を経験値稼ぎ程度にするなら、小6から中学校内容に入って、中3の1学期に準2級を3種類(英語・数学・漢字)そろえておく、という事も可能です。大学受験の第一関門である共通テストは英数は準2級で対応できるレベルですからね。中3ですでに大学受験レベルです。ハイレベル中学でやることを先にやっておくというイメージですね。それほど難しいことではないです。意外にすんなり理解してくれますよ。ただしこの状態ですと、公立中学に入ると授業が簡単すぎるという欠点がありますけどね。なんで?という話ですが・・・。
集団授業には授業レベルがあります
学校は集団授業なので普通に考えればその集団の中間くらいの層がついていける授業内容にすることが多いですよ。もちろんバリバリの超進学校は上位層のみを対象とした授業を展開して「黙ってついて来い」ですし、学力が低い地域の公立校は中間より下の生徒をターゲットにした授業を展開します。でも前者は落ちこぼれを多く出す原因となり、後者は上位層にとって無駄が多くなります。このような集団授業は、やる気、危機感、自己肯定感、コミュニケーション能力などの非認知能力も含めた総合的な能力向上、集団としても能力向上にはまあまあ向いているとは思います(最近はそれすらも怪しいなと感じますけど)が、一人ひとりを確実に向上させていくという学習指導には向いておりません。どちらにしても提供される授業レベルに合っていなければ、自分で頑張るしかありません。
ちなみに究極の選択肢として、最近はいい大学に入るために通信高校を選ぶという生徒も増えているみたいです。通信高校は行事も通学も部活も不必要な授業もありませんし、めんどくさい教師やクラスメイトとの付き合いもありません。大学を受験するのに高卒の資格がいるので通信高校でいいや、という生徒はじわじわ増えている感じです。さらにエリート高校を何らかの事情で中退した生徒も、エリート養成専門の通信高校を賑わせていますね。まあ確かにいい大学に行くための勉強時間を確保したいという点では、通信高校はめちゃくちゃ合理的です。多くの通信高校では課題の提出やテストは驚くほど簡単です。普通高校では1週間で30時間、それを1学年で35週間ほど拘束されますが、通信高校だと同じ単位を、半分どころか5分の1とかの時間でとることが可能です。恐ろしく合理的過ぎます。もちろん実習を伴う教科は校舎に行かないといけませんけどね。一点集中型のお子さんにはこんな合理的な話はありませんなぁ。ただし、まだまだ一般的とは言いがたいですけど。
時間の有利さは絶対
ただ集団授業でも個別指導でも時間が長ければ長いほど有利です。いい中学に入れたら、そこでは6年計画で良い大学に合格する手順(もっと言えば人生の視野や選択肢を広くさせること)を進めていきます。いい高校だと3年しかありません。しかし本人が小1で医者になりたいと本心から言えば、医学部受験まで12年あります。小学校の学習内容はその気になれば小3で終わらせることができると思います。ただしそれを計画的に取りこぼしなくやってくれる指導者に師事する必要があり、お母さまがやる場合は学習計画と学習内容の把握・指導と学力状態の把握までできることが理想的です。ちなみに私は勉強や体育や音楽など「できる子」「できない子」が「みんなと同じことをゆっくりする」というやり方には部分的に反対(※)です。
飛び抜けてできる子ができない子に合わせるということは、極言すればその飛び抜けた子は足を引っ張られていることになると感じています。小学校でみんなと歩調を合わせて行動する事は、気遣いや忖度、弱者・少数派への尊重などの社会性の能力の向上に寄与することは否定しませんし、勉強はできるけど体育は全然できないという場合などは、立場が逆転していい勉強になりますね。もっと言えば、私たちが見えない部分の非認知能力も同一学年の集団でもまれないと伸びないはず、と言われればそうかもしれません。ただ各能力向上にはホットタイム(最も効果が高い時期、臨界期とも言うらしい)というものがあり、学業に関しては小学校期がまさにその最盛期の入り口です。その時期に最高の状態を引き出させないであえて足踏みさせ、そしてそれを毎日毎時間やらされるなんて、これは最近文科省が言う「個を重んじる教育」なんだろうか、と思ったりしています。できない子が別室で授業を受けることが最近は増えていますが、出来過ぎる子もそれがあってもいいんじゃないんかな~と思っています。もう、才能が遊んでしまってもったいなさすぎてですね。できる子なんて小学校6年間の勉強は3年間で終わりますよ。公教育のせいで才能が封印されたままになっている、伸びしろが短くなっている、伸びる時間が強奪されているなんて思ってしまうぐらいです。公立の小中の生徒を担当していると、たまに宝石の原石がよく転がっています、いやマジで。まあ、その才能をどう活かすかは本人と親御さんが決めることなので私はさらっと報告して鼻息を荒くしないように努めていますけどね。
最終目的を見誤らないで
学生である間の最終目的は端的に言うと「いい大学に入る」でしょうか。もっと広い意味で言えば「将来の選択肢を最大限に増やす要素の中で、最も大きな位置を占めるであろう学力と最終学歴を最大に高めておく」という感じになるのではないか、と思います。例えば、高3になって「慶応行きたい」「最先端の情報科学を勉強してグーグルに入りたい」という具体的な希望を持った場合、その時点で偏差値が70と46ならどちらがその希望をかなえやすいか。高3で偏差値46だと慶応もグーグルも厳しいでしょうね。そのために高3時に偏差値70に近づけておくために何歳の時に準備を始めるか、という点ですね。小1から始めたら11年あります。高2から始めたら1年しかありません(高3の9月にはその近辺に到達していることが望ましいッス)。ちなみに、最も大事となるその辺のモチベーションは、情報量や成功体験、環境に左右されてだんだん成長していくので、外部の人間、特にその領域にまったく触れていない者がどうこう言ったところで、自分の意志で本気(マジ)で動く子は少ない印象です。たまに、いきなりそういうのが降りて来て急に生まれ変わる子や、才能に恵まれている非常識な子がこの生まれ変わる瞬間を迎えてスコーンと伸びたりもしますけど。
最後にーーー環境としての親御様
こういう話をすると、じゃあ私はどうしたらいいの?と聞かれます。どこかのページでも話しましたがお子さんの年齢や状況で出来る事・やるべき事は異なります。親御様の得意・不得意もあります。一般論はありますが、現場での適用の際は状況に合わせて適宜対応です。このサイトでは色々な状況ごとにこんな方法がありますよ的な情報は出しているつもりです。その適宜対応能力(いわゆる養育能力の1つ)は、今までの知識や経験値でさじ加減が変わります。今までお子さんの学力向上に関わる本を一冊も読んだことがない方がいきなり言われたとおりにやるのと、ある程度知識もトライアンドエラーの経験のある方がやるのとでは、その後の結果が全く異なります。特にお子さんが自立期(いわゆる反抗期)に入っていて、押しつけがましく関わると恐らく数年間はあなたの話を聞いてもらえないでしょう、環境としての親御様の立ち位置を大きく考え直さないといけなくなります。ですので親御様もお子さんと一緒にトライアンドエラーが必要です。エラい先生がおっしゃっていたことをそっくりそのまま適用しても学力向上に関してはあまり効果が出ません。当たり前ですが、前提条件(こういう子だったら、こういう状態だったら)がその先生が想定している状態と異なっていることがほとんどですから。そしてエラい先生がおっしゃっている前提条件に我が子を持って行くことがどれだけ至難の業か。それなら前提条件が同じような先生を探すことの方がいいかな、と。そうなるとたくさん読まないといけなくなりますね、同時に知識も増えてきます。親御様も一緒に成長する、とは、我が子に対して、目的を持ったアプローチをしてどれだけの結果を出し、フィードバックを持ち、次に活かせる二の手三の手をいくつ持っているか、が大事となります。エラい先生は結果ははっきり言ってくれています。そこに持って行くのにどれだけの手数を打てるか、それを勉強するのが親御様の仕事です、エリートに育てるなら。一緒に頑張ってまいりましょう!