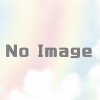才能を褒めるのは悪いことなのか
はじめに
最近、と言ってもここ20年くらいでしょうか、「褒めて伸ばす」教育が脚光を浴びておりますね。スパルタ教育なんてもはや昭和の遺物となりました(多分)。まあどっちがいいかなんてわかりません、その子自身が決めることです。そしてそれは10年とか30年とかが経過してから評価が少しずつ固まってくるのかな、なんて思いますけど。
褒めるのは才能?努力?結果?
そもそも、親の世代は「褒めて伸ばしてもらうこと」が当たり前ではなかったので、親が自分の子ども(私の場合は自分の生徒)にそれを使う場合、少し勉強が必要、というかというか心がけが変わることを意識しなければなりません。ただ褒めりゃあいいのか、というと、これまたちょっと違うんですね。そこで必ず話が出るのが、ほめるのは「才能か、努力か、結果か?」という点です。才能を誉めるというのは、その子が既に持っているもの、先天的に生まれ持ったものを誉めるということです。一方、努力を誉めるというのは頑張っているプロセス、結果は文字通りその向上した結果を誉めるというものですね。やはり今日において特によく推奨されているのはプロセスと結果ですね。才能を誉めるのではなく努力と結果、特に努力を誉めなさい、という論調が多い気はします。もちろん正論だと思います。以下、才能をほめることに焦点を絞って私見を書いていきます。
才能を褒めるのは悪い?
ここからが特に経験則な、印象論みたいな話になるのですけどね。まず確認しておきたいのは、才能を褒めて育ててもらっているお子さんの場合、彼らはただそこにいるだけで自分の自己肯定感が高まる、という経験を経ています。何も努力や工夫をしていないにもかかわらず「頭いいね~」なんて何度も言ってもらえるとか、親の着せ替え人形状態なだけなのに「まあ、超かわいい」なんて言ってもらえたりする、あれです。語弊を承知で言い換えると、このタイプの多くは「努力なしに他者から自信を手に入れた子どもたち」ですらあります(もちろんすべての子がそうではありません、自信がないタイプなのでほめ過ぎるぐらいがちょうどよいお子さんもいます)。この時大事なのは、「自信は行動を促す」ことが多い、という点です。経験則に裏打ちされていないのに行動します。それは身近で言うなら、調子にのって生意気になる、親や友人の目を気にしなくなるという事。見ている側は不安あるいは不満で仕方ないですよね。効率の悪い努力、何事も最後まできっちりやらない、計画を立ててやらない、調子に乗って中2病(本気出せばオレすごいから)、悪目立ちしてる等々。行動するけど効率が悪い、一貫性がない、結果が出ない、鼻につく等の悪循環につながっていく、そう思われていますね。だから才能を誉めるとろくなことがない、という論調になるのかなと思います。
こういった考え方や行動パターンは悪いのか
世の中的には、「こういう衝動的な行動や自信過剰な考え方に偏る可能性が強いから、才能を誉めるのはあまり良くない」という風潮があるのは知っております。私もそういう知人、生徒はおります。ですが、中学受験や勉強が苦手なお子さんが特にそうですが、同じような能力の子どもたちが集められ、同じカリキュラムで同じ勉強時間・同じ評価基準で、「はい、競争なさい」というのが今も昔も変わらない受験勉強の主流です。「なぜここにいるのかよくわからない」という状態の子が多いですね。能力が同じなら、自信のない子や行動できない子が最初に振り落とされています。そしてさらに自信を無くし、自分を守るために学ぶ意味に疑問を感じ始め、親御様に反感を募らせていく、と。そうなるくらいなら「行動できるようになるのなら自信過剰でもいいんじゃないか、取り残された時はまずは行動でしょう」、と強く言いたい。「行動しなくなった子」に行動させることがどれほど難しいことか。経験的にですが、行動している子に「いいね、惜しかったな。多分次はこうすると成績は跳ね上がるぜ、とりあえず算数だけでもやってみようか」などと「承認→点検→向上の希望」の順番で取り組ませることは比較的容易です。しかし、「行動のない子」はまず行動させるだけでも本当に時間も労力もかかりますし、もちろん結局動き出さないこともあります。でも例えば戦場(受験現場のことと思ってください)に取り残された時に、「あれはだめ、これはだめ、お前はダメ」なんて言われていたら何もできませんし、生還できませんよ。使えるものは何でも武器にする、どんな手を使ってでも這い上がる、生き残る。そういう自信とか行動が大事かと思います。「自信過剰な子ども」はこういうとき生還できる可能性が高まると感じています。確かに彼らは大人の側から見て鼻につくから「よろしくない、生意気だ」的な感情論が出て来ることは、職業柄否定しません、私も人間ですから(笑)。ですが我が道を走れるタイプなら、それを長所と捉えて、活かすように大人の側が対応を変えるべきかと思います。個人的には、全てをコントール下に置かれて完全制御された受験対応型チャイルドロボットより、「自信過剰な子ども」は個性があって指導は楽しいです。もちろん才能を誉めたら全員が天狗になるわけでもないですよ。そういうタイプのお子さんに合わせる、というかうまく伴走して操縦すらできる大人がそばにいれば大丈夫です。こういうポジションは、ご両親なら寛大な方の親御様が、塾なら個別指導型の指導者(そういう訓練を受けた者、専門としている者)がそれを担いますね。これこそが個性に応じた能力の伸ばし方の1つであるべきかなと思います。どうせ学校や集団塾ではクラスメイトにその自信を叩き折られてあるべき姿に戻りますから(笑)。こういう意味で最近私は「図に乗るから才能は誉めるな、努力を誉めろ」という風潮には少し疑問をもっているのであります。褒める所があるなら才能だろうが努力だろうが全部褒めてあげたらいいじゃん、その後の行動は大人の側が関わり合いの中で改善されるようにするべきだろう、と思います。
自立のはじまり
そもそも、子どもの自立ってこういうところから始まるもんではないでしょうか。分かってないのに「自分でやるんだ~」的な。それを大人は距離をもって見ている。しかし現代は、育てる子ども数も減って、家族や親せき、近所の人間関係も減ってお金と時間が余っています。まあお金は余ってませんけど。するとそのお金と時間と心のゆとりはお子さんに向くことになる、かもしれませんね。距離をもって見ているだけでは親御様自身が何か大切な仕事をすっぽかしているような罪悪感を感じ、ついつい手も口も出してしまう。ついでに金も。どんな意味での自信であれ、自信のある子どもは自分でやりたい、やれるはずという意識が強いですから自立も早いとは思います。もちろんそこら中で失敗して心を折られます。それをフォローするのが親御様、指導者の役割ですね。親御様や指導者が失敗を恐れて「型通りに育てるのが良い」と固執することは避けるべき、ですね。型通りで優秀になるならいいんです、そうはいかないお子様の場合は「型通り」なんて意味のないことではないでしょうか。そして型通りで優秀になるお子さんの少ないこと。個別指導をやっていますと、「型」って何よ?「一般論って役に立たない」みたいな感覚にすら陥ってきます。
お子さんの自立期には親御様は接し方を変えてみては?
自立期(反抗期)は、尊敬する人以外からの指示は基本的に受け付けない時期となります。そして親御様がお子さんから見て尊敬に値する人でないのなら(8割はそうでしょうね、感謝はしてますよ笑)、小学生低学年まで(この時期は無条件に親御様を尊敬しています)のような接し方はやめて、非常に簡単で効果の高い「才能を誉める」を実践するのはいかがでしょうか。もちろんどんどん調子に乗ってきます(笑)し、「俺はすごいんだよ」的に行動も変わってきます。いわゆる中2病ですけど。そこで親御様がやるべきなのは、その伸びきった鼻を折る環境や、伸びた鼻と同じぐらい心も成長させてくれる環境(人)を準備する事が重要になってきます。「褒めたら、自信がついて、行動する」はかなり現実的です。自信がない子ほど行動するまでに時間がかかります。でもですよ、だからといって、親をバリバリに無視する中2の娘に今日からいきなりお父さんが最高の褒め言葉と思う責め方で「○○坂の○○さんに似てるね」とか言い出しても「はぁ?」となりますから気をつけてください笑。「気をつける」とは、いきなりは効果が出ないのでしばらく続けるか、本人が喜ぶポイントを探る為に何でもかんでも褒めてみて娘の視線や言動を観察しなければならない、という意味です。会話ができないのは2~3年続きますから、本当はその前に種をまいておかないといけませんけど。ちなみに、そもそも行動全てを根っから嫌がるタイプもいるので、そういうタイプは褒めても多分動かないです。彼らは好きなこと以外、持っている才能だけでなんとかしようとしますし、心を許した人の言葉しか入ってきません。
才能も努力も結果もまずは全部褒める
ということで、ほめることがあるなら、才能も努力も結果も全部褒める、というのはいかがでしょうか?褒める所がない、という話をたまに聞きますが、それはお子さんに対して「揚げ足取り」になっているかもですよ。まずは褒めてみて、様子をじっくり観察ですよ、1ヶ月ほど。感謝と褒め言葉が同時のほうが効果が高いとか自分が言いやすいとか。勉強について才能を褒めるとやらないけどサッカーについては素人の私が褒めても鵜呑みで喜ぶとか。後者に関しては、サッカーは自分でも向上したいからすぐに効いたけど、勉強については苦手意識があるからもっと細かいところを褒めようとかのアイデアを出してまたトライです。そうやってお子さんをしっかり見て褒めていただき、個別指導者に報告していただければさらに指導しやすくなりますよ。ぜひ頑張ってみてください。手に負えないから放置もいいですが、その間何も手を考えないのと何かしらやってみるのとではその後、激しい自立期が収まったあとの可能性で差がつきますよ。