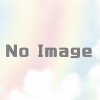教育ママにも2種類いるッス
はじめに
以前に中学受験を舞台にしたあるアニメで、「合格には『母親の狂気』が大切」なんて描かれて少し話題になりましたね。すごく攻撃的なフレーズで印象的です。しかも受験指導や早期教育をやっている者としては、言いたいことはすごくよくわかるので複雑な気持ちになります。このセリフを耳にすると「ならば母親が強いリーダーシップを持たねばならぬ」と妙なスイッチが入る親御様が実際にいらっしゃいます。誰の為の受験なのか再確認が必要ですな~となだめながらお話を進めるんですけどね。
教育ママには2種類います
ただですね、「狂気」という言葉から想像するのはやはり、お子さんに対する「尋常ではない圧力」です。ですので「狂気を持つ母親」という表現は少し怖いので、ここでは「教育ママ」(ちょっと古いな~)という感じの言葉にしておこうかなと思うのです。ということで、ここでいう「教育ママ」の定義などを少ししておきますね。「教育ママ」とは、学業をはじめとしてお子様の色々な能力向上に積極的に関わるお母様、という感じの定義にしておこうかなと思います。このようなお母様は大きく2種類に分けることができるかなと思います。
第一のタイプ
まずは、指示が感情的・抽象的で、フィードバック(振り返り)をしないお母様ですね。感情的に指示を出すというのは、お母様の「やるべき」「やるべきではない」の指示をお母様の機嫌で出すことですね。例えば毎日夜8時半からは勉強と決まっているのになかなか勉強を始めない場合、「もう8時40分でしょ、さっさと勉強始めなさい」と感情的に注意するタイプです。「なぜ8時30分にさっと動かなかったのか」を聞いたり考えたり、それまでのお子さん・親御様の行動を省みる、何か布石を打っておく等のことは多少あった方がいいですね、毎日ですとつらいですけど。次に抽象的な指示とは、「勉強しなさい」が有名です。例えば「今日は算数の〇〇のところをやるんじゃないの?」というのが具体的な指示です。ここまで言うと、「いやいや、母親はそこまで把握しないですよ」とおっしゃるお母様もいらっしゃいます。これね、正直な話、ここでかなり差がつきます。「中学受験の8~9割は親で決まる」というフレーズも聞いたのではないでしょうか。親御様の養育能力という指標です。「勉強しなさい」は一日に3回ぐらい言われるとすると、1年に1000回、3年で3000回聞くことになり、「あ、ちゃんとやらんと」というきっかけにはなりにくくなりますね。やらなくても致命的な危機が訪れることはない、「やらんでも大丈夫だった」「指示を無視しても大丈夫だった」が強化されます。ですが毎回違う「〇〇だから△△をやるべき」の指示は、お子さんと信頼関係が出来ていて的を射た話、あるいは致命的な危機が訪れることがわかっている話なら、お子さんの腰もスッと動きます。毎回同じ指示を出す割りにはお子さんの変化を全く分かってない人、ご自身はなにも努力していない(とお子さんに思われている)人からの指示であるなら、お子さんの自立期(反抗期)もあり、話を聞かなくなるのは当然です。そう言う親御様は申し訳ありませんがすでにお子さんの伴走者ではなく、言うだけ番長に映っています。心がつながってませんよ。言葉は心に届いていません。そんな「何言ってんのこの人?」という先生・上司いませんでした?
第二のタイプ(「中受は母親で決まる」を実践していらっしゃる方)
その逆で、指示が計画的・具体的で、検証を続けながら指示の選択肢をいくつか持っているお母様もいらっしゃいます。そういうタイプは、上の例で言いますと、定刻を過ぎても勉強をしないことが出てくることを見越して事前にこんな約束や共通理解をしています。
・あなたは〇〇中学高校に行きたいんだよね?と確認(押しつけではないような誘導がその前にあることが大事ですよ)。
・現状のあなたの成績は□□だから〇〇中学高校に到達するには、毎日△△くらいの勉強は必要。それは☆☆先生との面談で確認したよね。
・弱点はここ、得意はここ、次のテスト範囲はここ、前回と前々回はこんな感じでの勉強でこんな感じの成績だったから次はどうすべきか共通理解して「向上するぞ、できるぞ、させるぞ」の希望や気持ちを共有済み。強制(やりなさい)や否定(これがだめ)で確認させるのではないのですよ、素敵な将来像を共有できていたら最高ですね。ご両親・ご家族がお子さんにたくさんありがとうを伝えている場合、「医者はお客様(患者)から『ありがとう』を最もたくさん言ってもらえる幸せな仕事だよ。」など。
・お子さんの特徴(一点集中気味かバランス型か、気分屋かルーティーン型か、など)を把握した上で効率の良い言葉選びや環境設定をしている。
・こういうアプローチは、初めて想定したことがそのまますんなりうまく行くわけがないので、お子さんが幼いころからお母様自身が何度もトライアンドエラーを繰り返したり、そういう書籍・講演会・説明会で知識を得て実践をされている。その経験の上で、定刻に勉強を始めなかった場合はいくつかの理由の候補を知っており、それぞれにどうアプローチしたらよいかアイデアを持っていて距離感を大切にしている。
以上のように、第二のタイプのお母様は「先手を打ち、結果にいくつかの行動・言動の選択肢を持っている」というのが特徴です。過去と現在と未来がつながっている言動や行動ですね。これは一朝一夕では身につきませんので、勉強して日々トライアンドエラーです。
中学受験はほぼ母親で決まる
この2つのタイプの母親を比べると、一目瞭然ですね。第2のタイプの母親がお子さんの成績を上げられる可能性がグッと高くなります。この辺りは色々な書籍に書いてありますが、大事なのはそれぞれのお母様のアプローチは異なっていて良いので、自分のやり方を自分で作り上げる必要がある、という点、そしてお子様も十人十色なのでハウツー本の鵜呑みは危険、という点です。書籍の通りにしたのに成績が上がらないじゃないかっていう話は、教育業界でのあるあるです。また、第2のタイプで積極的になりすぎて過干渉になることもあります。それが先述の「母の狂気」かもしれませんね。母の狂気で合格したお子さんは、その後伸び悩みますよ多分。「伸び悩む」程度で済めばいいですけどね。まあ受験指導をしている身からすれば「いい大学に入る」ということを考えれば、中学受験で失敗しても高校受験で逆転すればいいじゃないですか。中学受験をしていれば高校受験・大学受験で有利になるのいう説は(本人が望んでいるなら)本当にその通りだと思っています。中1時点で見える景色が全然違いますからね~。このあたりがいわゆる「養育能力」とか「養育適性」という部分です。これは今からでも身につけることが可能ですよ。塾に入れてほったらかし、というのはお子さんの学力向上に置いてはあまり望ましくないような気もしますよ。過干渉でお子さんのメンタルを潰してしまうよりは100倍良いですけど。
塾選びは慎重に
そんなめんどくせーことできねーよー、という親御様のために学習塾というのがありますね。塾に入れて成績が伸びればあまり問題はありません。しかしいつまでたっても伸びない場合、伸びない原因を改善しなければなりません。その塾が改善や原因究明をしない場合、親御様はもうしばらく様子を見るか思い切って塾を変えるか、いっそのこと受験をやめるか、という選択を迫られます。そういう部分の改善は個別指導型のほうが対応はしやすいかと思いますよ。ちなみに今の小学生は上位校ねらいだとダブル塾も普通にいますね、可哀想ではありますけど。
ちょっとおまけ
ちなみに世の中には、一見すると「教育ママ」ではないのに、お子さんがものすごい向上を見せるケースも意外に多くあります。ほったらかしに見える、というやつですね。親御様が生まれもって養育適性に優れていたのではないか、お子さんが先天的にPDCAを回せてメタ認知を会得しているタイプかな、と感じることが多いですね。人間にも無限の能力・才能があるので、養育能力や適性が先天的に優秀な方がいても不思議ではありませんし、もともとそういう家庭で育てられそういう育ち方をした親御様(後天的に身につけたともいえますが)は自然とそういう育て方を選ぶ傾向も強いと思います。そういう親御様の「これくらいでいいんじゃない?」がお子さんにはとってもいい感じになる距離感を作っているんでしょうね、と。もちろん、その距離感はA君にはベストだけどB君にはベストとは限りませんからね。そういう親御様を参考にするのはいいと思いますが、真似はあまりおすすめしないですよ。色々と複雑な要因が絡んだ上でのその距離感ですからね。隣りの芝は青く美しいかもしれませんが、自分ちも同じ色に染めよう、何色使ってんの?などとは思わないことです。自分ちの芝が青く染まる方法は自分で探さないとダメです。
ご質問等がございましたら以下のメールまで遠慮なくどうぞ~。
渡嘉敷真仁:masatokashiki@gmail.com